「自然エネルギーを考える会」から提供を受けて、会報などを提供しています。
56.2016年4月電力自由化が始まりました。
2016年4月1日に「電力小売」が自由化されました。4月を機にしたあらたな動きと自由化を巡る政府アンケート結果が発表されたので紹介しました。資源エネルギー庁に設置されている「電力取引監視等委員会」は「電力・ガス取引監視等委員会」に改称されました。電気事業法等の一部を改正する等の法律が4月1日付で施行され、「電力取引監視等委員会」の所掌事務にガス事業法及び熱供給事業法に関する事務が追加されたことによります。2017年にはガスの小売りが自由化される予定です。4月1日段階では280の小売業者が登録されています。詳しくはファイルをダウンロードして下さい。
55.高野市長と自然エネルギーやスマートエネルギー都市を巡って懇談しました。
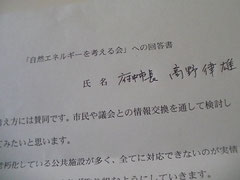
二期目の市長選で「スマートエネルギー都市への取組拡大」を掲げ、候補者に「会」が提出した6項目の質問に回答を寄せていた高野市長と懇談しました。9人の会員が参加し市長応接室で3月17日午後3時半から30分間、今回は、(1)スマートエネルギー都市(自然エネルギー都市)を目指す基本姿勢、(2)遅れている地球温暖化対策推進計画にもとづく世帯への太陽光パネルの普及、を中心に意見交換をしました。
54.府中市議会でも自然エネルギーの議論が行われるようになりました。
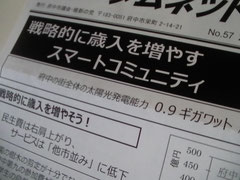
「自然エネルギーを考える会」は過去に2012年に自然エネルギー社会を目指す都市宣言に向けて大規模の署名運動を行ったほかに(1)市議会への「屋根貸し推進陳情」(2013年6月 可決)、(2)学校の屋上見学と教育委員会への環境教育上の格差早期解消の要望書(2014年7月) (3)環境基本計画に関連して行政への「新エネルギー建築の整備・見える化事業の推進陳情」(2014年7月)、(4)CSRによる学校へのパネル寄付に関する交渉(2015年1月)、(5)市長選にあたっての候補者への質問など市や市議会に働きかけてきました。時代の流れもあり、議員のなかでも自然エネルギー社会を展望した質問を行う例が最近、増えています。いくつかを紹介しました。
53.2016年3月に行われた展示会 「スマートエネルギーweek2016」の報告をしました。
展示会「スマートエネルギーweek2016」が東京ビッグサイトで3月2日~4日に開かれました。2012年以来紹介してきた太陽光関連の「PV Japan2016」をはじめ今回が二回目となる「電力自由化expo」や今年はじめての「エコハウス・エコビルディング」「バイオマス発電展」のほか、「風力」「スマートグリッド」「水素・燃料電池」「二次電池」「システム施工」などこの分野の総合的な展示会です。小売自由化の直前で、各分野の基調講演やセミナー(全体で227セッション)では自由化expoの東京ガスや関電などに多くの参加者があり第二会場が設営されるなど盛況でした。
52.2016年2月、いよいよ電力自由化が目前に迫ってきました。
年を越し、4月1日の電力自由化に向けてテレビコマーシャルなどが増えて急ににぎやかになってきました。昨年12月例会を行った前日の12月18日に「資源エネルギー庁電力・ガス事業部 電力市場整備室」が懸案の各電力会社からの託送料金の申請を認可したと報道しました。この結果を受けて、新電力会社は料金メニューを確定することができました。最新の動きと注意点を学びました。
51.府中市の高野市長が2期目の再選にあたって「スマートエネルギー都市」を公約しました。この内容について勉強しました。
1月31日の投開票で現職の高野市長が、再選されました。「自然エネルギーを考える会」はこの市長選を自然エネルギーの重要性をアピールする機会として捉え、お二人の市長候補に、「質問書」を送付し回答を得て、この内容をフェイスブックページで広く紹介し500人以上の方が閲覧しました。高野市長からの「回答」については、行政の長としてのお考えとして、より発展できるように働きかけたいと思います。選挙広報を見ると二人の候補者の選挙公約には、何等かの形で「自然エネルギー」に触れておりますが、ここでは高野市長の選挙公約である「スマートエネルギー都市への取り組み拡大」について、関連情報から考えてみます。
50.東京都下水道局の「スマートプラン」2014を学びました。
東京都の下水道は130年の歴史をもち多摩部でも99%完備しており、私たちの生活排水や都市部に溢れる雨水等を処理して、再び自然(川)に戻す仕事をしています。そのために22の水再生センーと87のポンプ所をもち都内における年間電力使用量(約860億 kWh)の1%強にあたる約9.8 億 kWhの電力(一般家庭約 27 万世帯の電力使用量)や都市ガス等の燃料を使っており都内最大級のエネルギー消費者でもあります。電気と燃料をあわせた1年間のエネルギー使用量は4,620TJ(テラジュール)で電気76%、燃料24%となっており2011年の大震災以降、料金値上げ等もあって30億円(20%以上)も跳ね上げり、電気の削減は大きな課題になっています。そこで「4つの取組方針」(➀再生可能エネルギー活用の拡大 ②省エネルギーの更なる推進エネルギー ➂スマートマネジメントの導入 ④エネルギー危機管理対応の強化)を数値目標とともに計画にまとめたものが「スマートプラン2014」です。2015年の1月にこの内容について勉強しました。
49.自然エネルギーを考える会は府中市の社会教育関係団体です。毎年1月に一年を振り返っています。会員用の文書ですが、公開します。

この会は、2012-2013年に行われた「府中市に”自然エネルギー社会をめざす都市宣言”を求める署名運動」のなかで誕生した学習・研究・運動団体です。2013年6月に会員が提出した「公共施設・用地での屋根貸し推進」の陳情が可決され、その後も学校への太陽光パネルの導入の推進等、機会を捉えて行政へも提案を行ってきました。この一年、政府は原発の再稼働を次々に決め、時代に逆行した動きをしましたが、12月のCOP21の合意など世界的には自然エネルギーに向かうあゆみは動かしがたいものになっています。この一年をふりかえりました。
48.2015年12月COP21がようやく合意しました。その概要を学びました。

世界が固唾を飲んで見守っていた地球温暖化対策に関するCOP21(パリ協定)が合意しました。この交渉に向けて世界の多くの自然エネルギーを推進する団体がアピールしました。合意の中身を学ぶとともにこの合意にしたがってどのように国内法が展開するのか注視する必要性を話しあいました。話題の多い一年でしたが、この一年を締めくくる議論をしました。
47.長野県の水力発電所の見学報告です。

長野県東部から佐久を経由して千曲川に流れ込む湯川は、山深い渓流ですが、浅間山の噴火で吹き飛んだ溶岩などが川端、川中に残り変化と起伏に富んでいます。
この流れのなかに古くからいくつかの水力発電所があり、多くは中部電力が管理しています。大正時代につくられたこの水力は日本の発電の歴史のなかでも、旧いほうに属しているだけでなく、自然エネルギーによる発電の一類型を学ぶことができると考えました。
1920年につくられた茂沢発電所はすでに95年の歴史をもっています。 大正時代につくられたこの設備が今も活かされ使われているという点に驚きを感じます。このほど関係者にお願いして地元の人たちとともに見学する機会があったの
で報告します。
46.電力自由化をまえに自治体の動きを調べてみました。
来年1月に府中市で市長選挙があります。
私たちは昨年、府中市で「自治体学校in府中」が開催されたのを機に三多摩の各自治体に自然エネルギーの導入状況について、アンケー調査を行いました。また3・11事故のあと府中市に「自然エネルギー社会をめざす都市宣言」を求める1万5000人を超える大規模な議会への陳情署名活動を行い、その後も公共施設の屋根貸し推進陳情を可決させ、地球温暖化対策推進計画にもとづく市内1割の世帯への太陽光パネルの早期導入、市民債による自然エネルギーモデルハウスの建設ETC.・・・様々な提案をしてきました。ドイツでは先進的な自治体の活躍が国の流れを変えてきています。自治体の動きを考えてみたいと思います。
名古屋大学の竹内恒夫研究室は昨年の秋、全ての都道府県・市町村(全1788団体、一部事務組合・広域連合は調査対象外)に対し、自治体のエネルギー政策に関するアンケート調査を行いました。回答数は 976件 (回答率54.6%)で域内の2020年CO2削減目標の有無・数値、エネルギーを冠する組織、エネルギー条例の有無・目的・措置内容、エネルギー計画の有無・目的・措置内容、域内のエネルギー需給構造の把握状況、エネルギーの個々の取組の内容などのほか、エネルギー行政の地方分権化の意向、さらに、電力小売自由化を見据えた自治体の小売事業者への参入の意向などを把握しています。私たちが調査を行った多摩30市町村のうち24自治体が回答しており、これらを紹介しながら考えてみます。
45.急ピッチで電力自由化に関して動きが始まっています。
小売自由化に向けて準備が進んでいることを報告しましたが、一か月経過し、2015年11月に入ってピッチがあがっています。内容は膨大ですが、その一部を紹介します。
前回、報告したときから登録小売事業が増えています。11月9日現在で16社増えて56社が登録されています。大手企業や子会社が多いという傾向は変わりませんが、フェイスブックの「みんな電力facebookコミュニティ」で市民的な情報発信をしている「みんな電力」(世田谷)も登録されました。すでに法人向けに「最大15%値引き」というオファーを行っています。10月31日に開かれた「ガス展」の日経新聞の報道記事では「東電はその35%に当たる2兆8千億円を独占してきた。首都圏の巨大市場を狙うのは東ガスや関電だけではない。楽天は丸紅と組んで電力参入を表明し、KDDIもJX日鉱日石エネルギーとの連携を模索する。早くも「東電包囲網」が広がっている。」としています。報道によると東電が社内でひそかに進めてきた新たに出現するライバルの分析。結果はいま東電が売っている電力の2割が奪われるという厳しいものだったとのことです。自由化とともにむしろ既存電力各社の独占が強化され、電力料金があがったというイギリスの轍だけは踏んで欲しくありません。
44.引き続き小売電力自由化の動きを引き続き学びました。
「新電力比較サイト」 http://power-hikaku.info/ 、「価格・com 電気料金」 (電力料金比較)http://kakaku.com/energy/、「エネルギー情報局」http://j-energy.info/、「比較電力com」http://hikaku-denryoku.com/list/pps などインターネット上ではすでに新電力各社の実情を比較することができるようなサイトが揃ってきました。また近いうちに電話やダイレクトメールでのオファーが盛んになるといわれています。ここで新電力の多くがどのような問題に直面しているのかを紹介します。
新電力が小売に参入する場合、既存の電力会社と比べて圧倒的に不利なのは、火力発電その他多額の投資を要する発電手段を持たず、供給能力に難があることです。そこで固定価格買取り制度のもとで一般家屋での導入も含めて、既存の電力会社が「買取り保留」をせざるを得ないほど普及した太陽光による発電電源を買い取ろうとしています。固定価格買取り制度は、東電など既存の電力会社だけでなく売電先が変わろうとも適用されます。そこで売電先を切り替えてもらうために「固定価格+1円」などのプレミアムをつけており、この動きはかなり広がっています。
43.「小売電力自由化」の準備が進んでいます。その準備の状況と課題を学びました。
新電力は9月18日の時点で762社が届け出ていますが、資源エネルギー庁の「電力調査統計」で7月に電力を販売した実績のある事業者は90社です。2016年4月から登録制に移行します。
いっぽう本年6月に成立した改正電気事業法等に基づいて、9月1日に電力取引の監視等の機能を一層強化するため電力取引監視等委員会が新たに設立され、この委員会の下に「電気料金審査専門会合」及び「制度設計専門会合」を設置されました。この専門委員会は頻繁に会議をひらくとともに、10月9日、電力取引監視等委員会は、小売電気事業を営もうとする者の40 件の申請について審査を行い、「適切でないと認められるものはなかった」としてに「登録小売電気事業者」としてリストを発表しています。新電力で最大手のエネット、電力会社のグループ企業ではケイ・オプティコムとダイヤモンドパワー、ガス会社では静岡ガス&パワーや北海道瓦斯、石油会社では昭和シェル石油や東燃ゼネラル石油のほか一般財団法人神奈川県太陽光発電協会等が入っています。小売電気事業者の登録審査は2段階に分かれていて、経済産業省が供給能力などをチェックした後に、電力取引監視等委員会が利用者の利益保護の観点から業務の実施体制などを評価することになっています。追加で申請のあった80件についても、審査が終了次第、順次登録を行ってゆく、としています。登録各社は料金プランなどを決めて営業活動に入ることになります。またパワーシフトを進める市民グループは9月21日にシンポジウムを開き、課題を明らかにするとともに、鋭意、準備中の会社をホームページで紹介していますが、「多くが、資本力や宣伝力で大手と圧倒的な差もあり、また様々な制度上のハードがあって、事業の立ち上げが厳しい状況にある」としています。準備の状況と課題を見てゆきましょう。
42.「電力改革を原発のない社会に活かそう」という熊本一規先生の講演会の概要です。
2015年7月18日に府中市内で熊本一規先生の講演がありました。
先生は1980年代から原発の経済学を研究し、一貫して市民のための学問を追求してきた研究者です。会からは6名が参加しましたが、質疑応答での答えも含めてあらためてその内容をおさらいしておきたいと思います。
41.PV-Japan2015展示会の報告です。
PV Japn2015が東京ビッグサイトで7月29日~31日に開かれました。出展数が昨年の160社に対して130社を減り来場者も昨年比で5000人ほど減って37000人でした。政府の消極的なエネルギー政策が反映していることは明らかで、派手な展示を行っていた中国勢のメーカーの小間が少なくなったのが印象的でした。
政府が最近、発表した2030年の電源構成で再エネ 22~24%、太陽光 7%(64GW)という消極姿勢はFIT導入後の急激な増加(導入量がすでに22GW,認定量74.5GW)を考えると確かに国内市場に水をさすものでした。専門セミナーでは市場関係者向けの「太陽光発電が生み出す新たな価値とは?」に参加しましたが、満員で真剣に模索する姿が感じられました。
40.「NHKエコチャンネル」には良質の自然エネルギー情報が掲載されていますので、紹介しました。
自民党の会合での言論弾圧問題などでなにかと懸案の多いメディアですが、NHK上層部の意向とは別に、番組制作者や、取材担当者は、現場の真実を報道することに熱意を傾け、その内容を国民に知ってもらいたいと熱望しています。その一端がネットで閲覧できる「NHKエコチャンネル」です。このチャンネルでは自然エネルギー問題をはじめ、広く環境問題の取材映像を系統的に整理して、提供しています。「話題になった貴重なニュースを見逃してしまった」「いまどんな話題があるのか知りたい」といったときにチェックすることができます。チャンネル構成の概要を紹介しますので、多くの方に親しんでもらいたいと思います。
39.「電力改革と脱原発」という書籍の紹介(その2)で、今回は発電のコストをどう考えるかを紹介しています。
筆者は各電源をどう割り当てるのが妥当なのかにつき前著では「値段は高いが、燃費のよい車と値段は安いが燃費が悪い車を、毎日の通勤と週一回の遠出の買い物にどう割り当てるか」に例えてわかりやすく説明しています。ベースロード電源としての資格は「高い設備利用率」が大前提となりますが、地震国日本では原発は電度5弱以下で自動停止する検知器を備えており、欧州や韓国のように90%程度の設備利用率を実現することができず、2011年以前の直近5年平均で64.7%という実績ではそもそも地震国日本で原発はこの点からもベースロード電源にならないことをしめしています。また発電設備を設置して「何年使える」と仮定するかによってコストは異なってきます。かつては「法定耐用年数」を用いていましたが、1985年からは「技術的耐用年数(40年)」を用いており減価償却費が大幅に減り、原発にとって有利になりました。筆者の説明はとてもわかりやすいです。
38.「電力改革と脱原発」という書籍の紹介です。(その1)
府中市の団体によって「電力改革の原発のない社会に活かそう」という講演会が7月18日に予定されており、熊本一規先生がお話されます。先生は長らく日本の電力システムを消費者の立場から見つめてきた方で、昨年「電力改革と脱原発」という著書を出しています。会として、この講演会に参加したいと思いますが、その予習を兼ねてこの本の一部を紹介します。
37.電力自由化の動きについて学びました。
周知のように)小売電力の自由化が2016年から始まります。戦後、我が国では、長らく民間電力会社10社の垂直一貫体制による地域独占と、総括原価方式により投資回収が保証される制度の下にありましたが.平成7年に発電部門において競争を導入し、また、平成12年以降、電気の小売事業への参入を 段階的に自由化し、全需要の約6割まで自由化範囲を拡大してきました。
しかし小売市場における新規参入者のシェアは自由化された需要の約4.2%に留まり一般電気事業者による地域を越えた直接的な競争もありませんでした。最近になって(1)電気料金を抑制する。(2)需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大するために(1)広域系統運用の拡大(2)小売及び発電の全面自由化。(3)送配電部門の中立性の一層の確保など、下記の予定で電力改革が進んでいます。
36.国会エネ調での議論の様子を紹介します。
国会には「エネルギー調査会準備会有識者チーム」があり環境・エネルギー政策や原子力政策に関する専門家、有識者で構成されています。「原発ゼロの会」には、現在10党・無所属の国会議員61名が参加しており、すでに2012年4月から47回の会合を重ねています。最近の47回目では電力自由化等の電力システムの改革に関して「さらなる原子力産業保護は必要か? 〜コスト、経営、原子力損害賠償」と題して、政府の政策を批判的に検討しています。議論の様子を紹介しました。
35.学校の環境教育などに使う扱い易い太陽光パネルなどを探してみました。
府中市内の小中学校の太陽光パネルを見学しましたが、いずれも大きながっちりした架台が置かれていました。まだ導入されていない学校も多いので、建材と兼用できるような扱い易いパネルでどのようなものがあるかを調べてみました。外国ではすでにパネルと建材の一体化が本格的に検討されているようです。
34.水素エネルギーの話題がホットです。メディアでどのように扱われているかを紹介します。
2015年1月にNHKで放映されたテレビシンポジウム「幕を開けた水素エネルギーの時代」などを紹介しました。特にドイツと日本の取り組みの違いなどに着目しました。
エネルギーの貯蔵手段として水素を液体の形にして運搬を容易にする点などに関心が寄せられました。
33.九州電力をはじめ電力各社が太陽光などで発電した電力を「接続保留」している問題について、学びました。
日本各地で「固定価格買取制度」のもとで認定を受けて発電が広がっていますが、せっかく発電した電力を電力各社が「接続保留」するという事態が起きています。欧米では考えられないことですが、なぜこのようなことがおきているのか、政府は電力各社をどのように指導すべきなのか、「接続可能量」というキーワードを取り上げて、勉強しました。
32.この一年を振り返りました。
「自然エネルギーを考える会」は府中市の社会教育関係団体です。毎年、2月末を年度末として一年の活動を振り返っています。会員用の文書ですが、公開します。
31.社会的貢献活動(CSR)で自然エネルギーの普及に貢献している企業があります。
企業は利益を追求していますが、社会的な公器でもあり、国民の要求に従ってさまざまな責任を負っています。このような企業活動の分野をCSRと呼ばれますが様々な活動を行っています。自然エネルギーの普及に力を注いでいる企業もあることを学びました。
30.資源エネルギー庁があらたな市町村の太陽光パネル等の導入データをの発表を開始しました。
私たちの市町村に太陽光パネルなどがどの程度導入されているかについては2014年の8月までは市町村にまで立ち入ったデータは発表されていませんでした。固定価格買取制度が発足したのちは、自宅で使いながら余った電力を売電する形の申請もすべて把握されているので、データそのものは存在していましたが、今回の発表でやっとわかるようになりました。このデータを利用すれば導入の進展状況を知り、自治体間の比較をすることも可能になりました。
29.首都圏で市民が力を合わせて電力を生み出す動きが活発になっています。
今年2014年5月23日に全国で誕生している共同市民発電のネットワーク組織「全国ご当地エネルギー協会」が発足し40近い団体が、2016年からの予定の電力の小売り自由化も見据えて、「地域主導で自然エネルギーを広めるため」の連携が始まりました。またこれに先立って2014年2月には市民共同発電に取り組む人々のネットワーク組織である「市民電力連絡会」が発足しています。会合に参加したので報告します。
28.2014年後半に話題になった電力会社による再生可能エネルギーの「接続保留」とは・・・・欧米では考えられないことが起きています。
2014年の8月あたりから各電力会社の状況が表面化し多くのメディアで報道されるようになりました。経産省では総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会に6月17 日に新エネルギー小委員会を設置しその議事録の要旨には「一部地域では、接続容量の上限に達しているため、接続が制限されている。今後、他の都道府県においてもこうした事例が発生することが予想されるため、適切な対応策や情報開示が必要」と指摘しています。報道のなかには「太陽光バブル」等の言葉を使って正確さを欠いたものがありますが、関係者による直接の情報にもとづいて冷静に事態を見る必要があります。欧米では電力会社が手段を講じて責任をもって接続することになっており、まったく問題になっていません。
27.農作物の生育と太陽光発電を両立させる「ソーラーシェアリング」について学びました。
ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うことをいい、農水省では、この発電設備を「営農型発電設備」と呼んでいます。太陽のエネルギーを農業と発電で分け合う(share シェアする)という意味でイメージとしてもわかりやすいのですが、英語にはこの言葉はなく、co-location という言葉で説明しているようで、インターネットではフランス、イタリア、アメリカなどの先進的な例を見ることができます。原発被害の跡地で農業再生に挑む南相馬市では地域再生の重要な柱に位置付けて取り組み始めています。「会」としても、見学などをしてより理解を深めることができればと思います。
26.会員で回付閲覧したDVD「十万年後の安全」の感想文集です。
2014年のはじめに「会」で「十万年後の安全」というDVDを購入して回付閲覧しました。何名かの方から感想が寄せられたのでまとめました。
25.PV Japn2014は東京ビッグサイトで7月30日~8月1日に開かれ、新しい技術のうねりを感じさせてくれました。
太陽光発電協会(JPEA)では「PV OUTLOOK2030」というビジョンを発表し更新していますが、固定価格買取制度が役割を終える時期を想定しても2030年までに累積導入量を100gwhと想定しています。日照時間を勘案してその稼働率が12%とすると一基1gw(100万kwh)の原発の稼働率が80%とすると原発15基分ということになります。太陽光エネルギーの巨大さと、これをいかに上手に利用するか・・・様々な技術の進展ぶりが窺える大事な展示会です。
24.「メディア番組から学ぶ自然エネルギーシリーズ」の6回目としてアメリカのシェールガス革命やカナダのオイルサンドなど地下の化石資源をさらに掘り出そうとする動きを批判的に学びました。
NHKは「エネルギーの奔流」という二回シリーズを放映し2014年8月に再放映しました。題して「膨張する欲望」(第一部)「欲望の代償 破局は避けられるか」(第二部)。まるで人々が悪いかのような見出しですが、自然エネルギーへの出口を示唆するものとして批判的にその内容を紹介しました。
23.市民発電などを考える場合、まず資金が問題になります。すでにはじめている団体などが採算や資金の計画をどのように考えているのか・・・を考えてみました。
すでに市民が集まって団体を結成し、発電の場所を探し、資金を集めて発電を開始している団体では、いろいろな苦労をされています。なかでも将来にわたる採算計画は大事な問題です。このことについて書かれた書籍を紹介しながら、考えてみました。
22.三多摩各地の自然エネルギーに向かう動きについて学びました。
三多摩の各地域でも自然エネルギーに向かう市民発電などの動きが広がっています。これらの動きを調べてみました。三多摩自治体学校in府中の分科会で「市民発電とみんなのエネルギー」という分科会を企画するきっかけになりました。
21.府中10小の見学をしました。発電の様子がよくわかりました。

この学校は屋上に太陽光パネルの設置のほかに緑化も施されており、見学に訪れる学校関係者も多いとのことです。発電の様子もよくわかり、生徒への環境教育上の配慮もありました。
私たちはこれらの見学を通じて、教育委員会に「要望」を提出しました。
20.全国の小中学校への太陽光パネルの導入に関する現状を学びました。
市内の学校の太陽光パネルの見学にあわせて、全国の小中学校への太陽光パネルの導入に関する現状を調べました。次の時代を担う生徒たちへの環境教育の一環で国から半額の補助が出ており、会計検査院も「パネルを生かしてしっかり環境教育が展開できているか」という点を重視しています。
19.府中5中の太陽光パネルを見学しました。
2014年4月22日、十数名で府中5中の太陽光パネルを見学しました。副校長の案内で屋上にあがりこれを取り付けたメーカーの説明を受けました。この見学には市の職員の方もいっしょに参加しました。
18.ほぼ年に二回、自然エネルギーに関する展示会があります。
「PV.・・・・」と題した再生可能エネルギーに関する大規模な展示会が約半年に一回開かれており、技術の進展状況がよくわかります。こうした展示会があることを市の担当職員にも紹介し、業務として参加できるように市長さんにも「市長への手紙」でお願いしました。今回は、パネルの軽量化や屋根材としてパネルを一体化する技術を中心に学びました。
17.2014年3月末から東京都がインターネットに公開した「ソーラー屋根屋根台帳」について学びました。
東京都は2014年3月26日からインターネット上に「ソーラー屋根台帳」を公開しました。ドイツのボン市など欧州の先進都市ではすでに行われていたことですが、都内の建物家屋の屋根の状態を飛行機を飛ばして調べ、日射量データなどと組み合わせてその屋根の潜在発電量を推計して表示するものです。グーグル・マップのように住所から屋根を選びクリックすると、数値が出てきます。「我が家はどのくらい発電できるのか」がわかります。こうした情報が広がることで太陽光の利用に対する関心が広がることが期待されます。
16.自然エネルギー導入の現状について、NHK報道をきっかけに学びました。
2014年3月4日、NHKのクローズアップ現代で「なぜ進まない 再生可能エネルギー」と題して報道しました。固定価格買い取り制度のもとで申請された多くのメガソーラーの計画が、いまだに実施されていない現状を伝えました。この報道に背景に何があるのか、について学びました。
15.府中市の第二次環境基本計画について学びました。
東京府中市が2014年4月に「第二次環境基本計画」を定めました。この環境基本計画は、府中市の法律である「条例」にもとづくもので、いわば法的な拘束力を伴うものです。第一次の計画でも「省エネルギーモデル建築の導入」など意欲的な計画を立てていましたが、残念ながらいまだに実施されていません。今回の第二次計画は、3・11事故を受けて市民が自然エネルギーへの要望を強めていることを受けて「新エネルギーモデル建築の導入と見える化」などの計画をかかげています。良い計画は早期に実施すべきです。
14.ハワイの自然エネルギーについて調べました。
ハワイは日本人に馴染みが深く、同じ島々が集まった生活地です。ハワイで自然エネルギーをどのように考え、生かそうとしているか調べました。明確な目標を掲げています。島国日本にとっても大きなヒントがあります。
13.政府のエネルギー基本計画について検討しました。
政府は2013年の12月に「エネルギー基本計画への意見」という関係機関の答申書を発表し、これへの国民の「パブリックコメントを求める」という形であたらしいエネルギー計画を策定しようとしています。「原発は基盤となる重要なベース電源」と位置付けるなど新しいエネルギー社会をめざす立場からみると、従来の政府方針から後退したものになっています。会員のなかにもパブリックコメントを提出した方がいます。
12.折に触れて世界のエネルギー事情を学んでいます。
11.自然エネルギー先進地域で起きていることについて学びました。
静岡県は年間の日射量が、多く太陽光パネルの導入も全国的に進んでいます。そのなかでも掛川市は、高い目標を掲げて種々に社会実験を試みています。「かけがわモデル」といわれる取組みを学びました。より普及させるためには、多くの市民に技術的に懇切丁寧な情報を提供し続けることが大切です。
10.「自然エネルギーを考える会」の一年の活動をまとめました。
府中市の「自然エネルギーを考える会」は都市宣言を求める署名運動のなかで生まれましたが、その後、地道に学習活動を行っています。一年間の活動をまとめています。興味のある方は「お問い合わせ」でご連絡下さい。
9.府中市の生涯学習センターで「自然エネルギーへの期待と課題」という連続講座が開かれました。
2013年の11月から12月にかけて府中市の生涯学習センターで「自然エネルギーへの期待と課題」と題する連続講座が開催されました。「会」のこの講座の開催にあたり、講師の先生への打診など協力させていただきました。この講座を受講された方のなかから「会」に参加された方もいます。
8.府中市の生涯学習センターのボランティアグループの「悠学の会」でお話しました。
府中市の生涯学習センターには、市民のための学習講座などを企画する「悠学の会」というボランティアグループがあります。悠学の会の「学びのサロン」でお話しました。
7.太陽光パネルを各市で見かけますが、その進展ぶりを統計データで調べました。
6.中欧のエネルギー事情を紹介しました。
ドイツやフランスの例はよく紹介されていますが、ヨーロッパの他の国はどうなっているのだろう・・・オーストリアやハンガリーのエネルギー事情の一端を紹介しました。
5.住民参加型地方債で自然エネルギーを推進している例を学びました。
多くの市民が、「新しい自然エネルギーの具体化に貢献したい」と考えた場合、まず問題になるのが財政調達(ファイナンス)の問題です。自治体がかかわることで市民がリスクや負担感を感じることなく進めている例について学びました。
4.展示会にいって勉強しました。
3.全国に広がりつつある市民共同発電の財政上の課題について学びました。
2.日本で有望と言われる地熱発電について学びました。
1.「会」の勉強会を本格的に開始しました。
「自然エネルギーを考える会」は2013年度も府中市の社会教育関係団体、フロアセブン、府中市NPOボランティアセンターなどに登録し、認定を受けて活動を行っています。
原則的には、毎月第三土曜日の午前中に中央文化センターで勉強会を行ないます。
自然エネルギーに興味がある方は奮ってご参加下さい。
 府中市に”自然エネルギー社会をめざす都市宣言”を
府中市に”自然エネルギー社会をめざす都市宣言”を